詩経という中国最古の詩集に「胆大心小」(たんだいしんしょう)というフレーズがあります。
「胆は大きく、心は小さく」だと意味がちょっとわかりにくいですね。
おおよそですが、
「深い淵に臨んだり、水面に張った氷の上を歩く時のように、慎重にふるまいなさい。
同時に、強大な軍勢が城を守っているかのように、自信をもって大胆にふるまいなさい」
という意味。
まったく逆のことを同時に言っているようですが…………。
「大胆と細心のバランスが大切」ということですね。
「考える」というのは複数の要素を考慮して結論を出すということですから、
「バランス」は常に意識していないといけないことです。
(意識しなくても、結果的にバランスの取れた決断ができれば、
それはそれでいいのですが)
2500年前から、こんなことを考えていたとは、人間はけっこう賢いなと思います(笑)
さて、大人になる準備として、様々なことを学ぶ小学生が多くの時間をさく算数という科目。
この科目には、その要素が詰まっています。
例えば、計算問題を間違えないようにあまりに多くの時間と手間を割きすぎては、後半がおろそかになります。
また、一方で急ぎすぎても雑になっても、満足な結果は得られないでしょう。
「じっくり」
と
「急げ!!」
そのバランスをとることが大切になります。
この感覚は頭でっかちな理屈・理論ではなく、子どもたちが多くの問題を解く中で自然と体得していくことです。
つまり、
「これは確実に合っている。
見直しはもう完了した。
もう1秒もさく必要はない!
さっさと次にいくぜ!!」
「いちおう、答えらしきものは出たけれど、これはまだ自信がもてない。
あとで要検討だ!」
という感覚を持って、解き進めていく必要があります。
それを区別し、色分けしてみていくことがとても大事なんです。
ですから算数は、どんな時も頼るべき黄金のルールを子どもに授ける、という科目ではありません。
最小限の知識と適切な問題を与えて、常に生徒が頭を使い続けられるように見守るのが算数の教授法ということになります。
胆大と心小。
どちらも大切なんですね。
ですが、僕は子供たちに伝えるのには、〇〇のほうをより大切に考えるようにといつも話しています。
どちらだとお思いになりますか?
それまで重いテーマではないのですが、
次回に続きます。
↓ブログ更新のモチベーションとして2つのブログランキングに登録しています。
ふーん、なんとなく話の展開はわかった!! と思ってくださった方はクリックをお願いします。
クリックはそれぞれ1日1回まで有効です。
にほんブログ村
中学校受験ランキング
【中学受験】算数も胆大心小でいこう(前編)




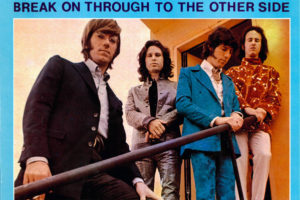








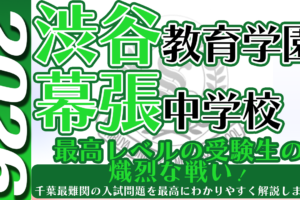





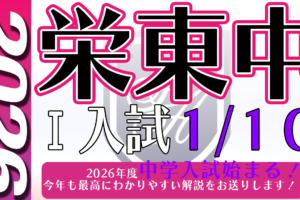
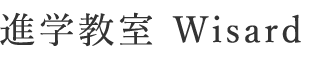
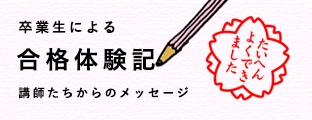
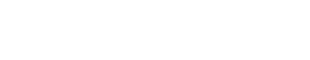
コメントを残す